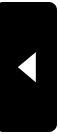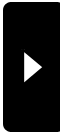2021年12月11日12:00

■キリスト教のお墓の特徴■
キリスト教では、死者は最後の審判の日に肉体に戻り復活する
という思想に基づき「土葬」を行うのが本来の姿ですが、
日本では、多くの自治体で土葬が禁じられているため火葬を行います。
世界的にも火葬が増えてきたこともあり、
カトリックでも2016年にローマ法王が、火葬を認める指針を明らかにし、
遺灰を教会の管轄地に収めるよう指示しています。
その場合キリスト教では、亡くなった人は天に召されると考えるため、
必ずしもお墓は必要ではなく、納骨堂に遺骨を納めるスタイルも普及しています。
お墓を設ける場合でも、先祖代々をまつる仏教とは違い
1人で1つの墓が基本となります。
キリスト教にもカトリック、プロテスタント、
聖公会、正教会など多くの流れがあり、
どのグループでも墓石の素材やデザインに制約はありませんが、
十字架が刻まれるのが一般的。
墓石は、仏教のものと比べ石の高さが低めで
「オルガン型」「プレート型」などと呼ばれます。
墓石に刻む文字にも特徴があります。
日本の仏教では、墓碑の正面に「〇〇家代々墓」など
家(いえ)の名前を刻むことが大半。
キリスト教では、故人の名前や洗礼名のほか、
聖書の一節、賛美歌などが刻まれます。
線香を供える習慣がないので、香炉はありません。
その代わりに、ろうそくを立てる場所を設けます。
■キリスト教と仏教のお墓はどう違う?■
まず、仏教とキリスト教では、
死後の世界についての考え方が異なります。
日本の仏教では先祖を「仏」として崇拝し、
お墓は「肉体の魂が眠る場所」で、自宅の仏壇の位牌が
「精神の魂が眠る場所」だと考えています。
このため、彼岸やお盆など、決められた日にお墓参りや法要を行い、
先祖代々のお墓を継承して、守ってゆく慣習が根付いています。
一方、キリスト教では、死は新たな人生の始まりであり、
死後の魂は地上に留まることなく
「天国に召される」「神の元へ凱旋する」と考えます。
ですから、お墓は故人の魂が眠る場所ではなく、
あくまで、思いを馳せるための「記念碑」という意味合い。
また、先祖を「仏」として崇拝する思想もありませんので、
お墓で供養を行うという感覚はありません。
もちろんキリスト教でも、故人を偲ぶ追悼式や集会は行いますが、
それらの催しは、教会などお墓以外の場所でも行われます。
■キリスト教のお墓を建てる場所は?■
お墓を建てる時には、まず場所の確保が不可欠です。
仏教寺院にキリスト教式のお墓を建てるわけにはいきませんので、
生前の所属教会の墓地、公営の霊園、宗教を問わず
利用できる民間の霊園が候補となります。
カトリック系や聖公会では、生前の所属教会が
所有する墓地に建てるケースが多く、
プロテスタント系各派は、統括団体の日本基督教団が
管理する墓地を利用するのが一般的。
教会の墓地に埋葬を希望する場合は、
その教会で洗礼を受け信者になる必要があります。
■キリスト教の納骨■
仏教の場合には、四十九日の法要を終えて納骨するのが一般的。
カトリックの場合、7日目に行われる追悼ミサの翌日か、
その1か月後、プロテスタント各派では1か月後の召天記念日に納骨します。
火葬が終わり納骨を迎えるまでは、
自宅や教会で、遺骨・遺灰を保管し、祈りを捧げます。
納骨式では、聖書朗読、説教、賛美歌合唱が行われ、
最後に全員で祈りを捧げます。
その後は、カトリックや聖公会などでは、
神に召されたすべての人へ祈りを捧げる日として、
11月に礼拝を行うことが多く、
プロテスタント各派では亡くなってから、
5年目までの召天記念日に、
墓前で記念会を開く場合が多いようです。
キリスト教のお墓について≫
カテゴリー

■キリスト教のお墓の特徴■
キリスト教では、死者は最後の審判の日に肉体に戻り復活する
という思想に基づき「土葬」を行うのが本来の姿ですが、
日本では、多くの自治体で土葬が禁じられているため火葬を行います。
世界的にも火葬が増えてきたこともあり、
カトリックでも2016年にローマ法王が、火葬を認める指針を明らかにし、
遺灰を教会の管轄地に収めるよう指示しています。
その場合キリスト教では、亡くなった人は天に召されると考えるため、
必ずしもお墓は必要ではなく、納骨堂に遺骨を納めるスタイルも普及しています。
お墓を設ける場合でも、先祖代々をまつる仏教とは違い
1人で1つの墓が基本となります。
キリスト教にもカトリック、プロテスタント、
聖公会、正教会など多くの流れがあり、
どのグループでも墓石の素材やデザインに制約はありませんが、
十字架が刻まれるのが一般的。
墓石は、仏教のものと比べ石の高さが低めで
「オルガン型」「プレート型」などと呼ばれます。
墓石に刻む文字にも特徴があります。
日本の仏教では、墓碑の正面に「〇〇家代々墓」など
家(いえ)の名前を刻むことが大半。
キリスト教では、故人の名前や洗礼名のほか、
聖書の一節、賛美歌などが刻まれます。
線香を供える習慣がないので、香炉はありません。
その代わりに、ろうそくを立てる場所を設けます。
■キリスト教と仏教のお墓はどう違う?■
まず、仏教とキリスト教では、
死後の世界についての考え方が異なります。
日本の仏教では先祖を「仏」として崇拝し、
お墓は「肉体の魂が眠る場所」で、自宅の仏壇の位牌が
「精神の魂が眠る場所」だと考えています。
このため、彼岸やお盆など、決められた日にお墓参りや法要を行い、
先祖代々のお墓を継承して、守ってゆく慣習が根付いています。
一方、キリスト教では、死は新たな人生の始まりであり、
死後の魂は地上に留まることなく
「天国に召される」「神の元へ凱旋する」と考えます。
ですから、お墓は故人の魂が眠る場所ではなく、
あくまで、思いを馳せるための「記念碑」という意味合い。
また、先祖を「仏」として崇拝する思想もありませんので、
お墓で供養を行うという感覚はありません。
もちろんキリスト教でも、故人を偲ぶ追悼式や集会は行いますが、
それらの催しは、教会などお墓以外の場所でも行われます。
■キリスト教のお墓を建てる場所は?■
お墓を建てる時には、まず場所の確保が不可欠です。
仏教寺院にキリスト教式のお墓を建てるわけにはいきませんので、
生前の所属教会の墓地、公営の霊園、宗教を問わず
利用できる民間の霊園が候補となります。
カトリック系や聖公会では、生前の所属教会が
所有する墓地に建てるケースが多く、
プロテスタント系各派は、統括団体の日本基督教団が
管理する墓地を利用するのが一般的。
教会の墓地に埋葬を希望する場合は、
その教会で洗礼を受け信者になる必要があります。
■キリスト教の納骨■
仏教の場合には、四十九日の法要を終えて納骨するのが一般的。
カトリックの場合、7日目に行われる追悼ミサの翌日か、
その1か月後、プロテスタント各派では1か月後の召天記念日に納骨します。
火葬が終わり納骨を迎えるまでは、
自宅や教会で、遺骨・遺灰を保管し、祈りを捧げます。
納骨式では、聖書朗読、説教、賛美歌合唱が行われ、
最後に全員で祈りを捧げます。
その後は、カトリックや聖公会などでは、
神に召されたすべての人へ祈りを捧げる日として、
11月に礼拝を行うことが多く、
プロテスタント各派では亡くなってから、
5年目までの召天記念日に、
墓前で記念会を開く場合が多いようです。