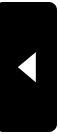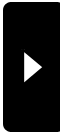2021年12月21日12:00

お墓参りで線香をあげる意味
実は、お墓参りでお線香をあげることは、仏教的な意味合いだけではありません。
昔の人たちの知恵も含まれており、とても意味があることです。
では、どのような意味が込められているのか、説明していきましょう。
まず一つ目として、私たちが来たということを
ご先祖さまや故人にお知らせするために、お線香を手向けます。
人のお宅を訪問する時、まず、玄関のチャイムを鳴らしますよね?
このチャイムを鳴らすという行為が、お墓の場合は、
お線香を手向けることになります。
二つ目としては、お線香の香りがご先祖様や仏様に
食事を捧げるという意味を持っていることです。
言い換えると、良い香りを食べて頂き、
ご先祖様や仏様に喜んで頂くことになります。
そして三つ目として、お線香の香りは、場所や人を清めて、
浄化してくれるものとされています。
お墓参りでお線香を手向けるということは、
お墓だけではなく、お墓参りをする人も浄化してくれるのです。
そのため、清められた状態でお参りをすることができます。
更に、埋葬のスタイルが土葬だった頃には、お墓でお線香を焚くことで、
お線香の香りが死臭を消してくれる効果もあったそうです。
お線香がまだ無かった時代には、お香や香木をお墓に手向けていました。
このことからも、「香り」がお墓参りでは、とても重要な意味を持ちます。
ちなみに、お香や香木からお線香に変わっていったのは、
簡単に使える細い棒状であるお線香が開発され、普及したことによります。
お墓参りでの線香のマナー
一般的に、お墓参りでは一束単位で持っていきます。
これは、そのまま束の状態で墓前にお供えする場合もありますが、
一緒にお墓参りに行った方々に分けるためでもあります。
お墓参りでのお線香の供え方は、宗派や地域によって様々。
束をそのまま横にして備える場合もありますし、
束をばらして、決められた本数のみをお供えする場合も。
また、お線香を置く香炉の広さによっては、
一束ではなく、半束をお供えする場合もあります。
初めてお墓参りに行く場合は、家族や周囲の方に、
その宗派や地域の作法を聞いておくと良いでしょう。
線香をあげる本数
こちらでは、一人ずつ、必要な本数をお供えする場合の
宗派毎の本数と作法についてご紹介します。
お供えする時には、本数だけでなく、
置き方にも作法がありますので、注意が必要です。
-臨済宗:1本を香炉の真ん中に立てます
-日蓮宗:1本を香炉の真ん中に立てます
-曹洞宗:1〜3本を香炉の真ん中に立てます
-浄土宗:1〜3本を香炉の真ん中に立てます
-日蓮正宗:1〜3本を横に寝かせます
-浄土真宗:1本を2〜3本に折り、横に寝かせます。
お線香をおるのは、香炉のサイズに合わせるためとなりますので2もしくは3本。
しかし、4本以上に折ることはありませんので、注意が必要です。
-天台宗:3本を香炉の中で、香炉の手前に1本、奥に2本、
自分から見て逆三角形になるように立てます。
-真言宗:3本を香炉の中で
お線香について 後編≫
カテゴリー

お墓参りで線香をあげる意味
実は、お墓参りでお線香をあげることは、仏教的な意味合いだけではありません。
昔の人たちの知恵も含まれており、とても意味があることです。
では、どのような意味が込められているのか、説明していきましょう。
まず一つ目として、私たちが来たということを
ご先祖さまや故人にお知らせするために、お線香を手向けます。
人のお宅を訪問する時、まず、玄関のチャイムを鳴らしますよね?
このチャイムを鳴らすという行為が、お墓の場合は、
お線香を手向けることになります。
二つ目としては、お線香の香りがご先祖様や仏様に
食事を捧げるという意味を持っていることです。
言い換えると、良い香りを食べて頂き、
ご先祖様や仏様に喜んで頂くことになります。
そして三つ目として、お線香の香りは、場所や人を清めて、
浄化してくれるものとされています。
お墓参りでお線香を手向けるということは、
お墓だけではなく、お墓参りをする人も浄化してくれるのです。
そのため、清められた状態でお参りをすることができます。
更に、埋葬のスタイルが土葬だった頃には、お墓でお線香を焚くことで、
お線香の香りが死臭を消してくれる効果もあったそうです。
お線香がまだ無かった時代には、お香や香木をお墓に手向けていました。
このことからも、「香り」がお墓参りでは、とても重要な意味を持ちます。
ちなみに、お香や香木からお線香に変わっていったのは、
簡単に使える細い棒状であるお線香が開発され、普及したことによります。
お墓参りでの線香のマナー
一般的に、お墓参りでは一束単位で持っていきます。
これは、そのまま束の状態で墓前にお供えする場合もありますが、
一緒にお墓参りに行った方々に分けるためでもあります。
お墓参りでのお線香の供え方は、宗派や地域によって様々。
束をそのまま横にして備える場合もありますし、
束をばらして、決められた本数のみをお供えする場合も。
また、お線香を置く香炉の広さによっては、
一束ではなく、半束をお供えする場合もあります。
初めてお墓参りに行く場合は、家族や周囲の方に、
その宗派や地域の作法を聞いておくと良いでしょう。
線香をあげる本数
こちらでは、一人ずつ、必要な本数をお供えする場合の
宗派毎の本数と作法についてご紹介します。
お供えする時には、本数だけでなく、
置き方にも作法がありますので、注意が必要です。
-臨済宗:1本を香炉の真ん中に立てます
-日蓮宗:1本を香炉の真ん中に立てます
-曹洞宗:1〜3本を香炉の真ん中に立てます
-浄土宗:1〜3本を香炉の真ん中に立てます
-日蓮正宗:1〜3本を横に寝かせます
-浄土真宗:1本を2〜3本に折り、横に寝かせます。
お線香をおるのは、香炉のサイズに合わせるためとなりますので2もしくは3本。
しかし、4本以上に折ることはありませんので、注意が必要です。
-天台宗:3本を香炉の中で、香炉の手前に1本、奥に2本、
自分から見て逆三角形になるように立てます。
-真言宗:3本を香炉の中で