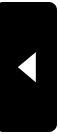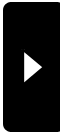2021年12月22日12:00

水をかける道具の種類
お墓に水をかける基本的な道具は水桶と柄杓です。
水桶(手桶ともいいます)とはその名の通り水を入れる桶で、
お墓参りでの水かけや暑い季節の打ち水などに使われます。
柄杓とは水をくむための道具です。
神社やお寺の手水舎で身を浄める際の道具として
置いてあるものをイメージしていただけると分かりやすいと思います。
これらは大体の墓地や霊園で誰でも使えるように貸し出されていますが、
そうでない場合には自分で用意する必要があります。
用意できない場合は、ペットボトルや綺麗なバケツも
水をかける道具として代用できます。
お墓参りで使う水桶と柄杓の値段
自分たち専用の水桶と柄杓が欲しい場合や、墓地や霊園での貸し出しが無く、
購入をしようと思っている場合には仏具店や
ネット通販、ホームセンターなどで購入できます。
プラスチック製や木製など様々な種類があるので、
値段も2000円前後から数万円前後まで幅広くあります。
水桶と柄杓のセットで売られていることが多いですが、
単体で販売されているものもあり、柄杓だけの値段だと300円前後から、
水桶だけの値段だと2000円前後から購入ができます。
できるだけ高いものを購入しなくてはならないなどのルールはないので、
自分が水桶に使うことのできる費用と相談して購入してください。
なかには水桶に家名や家紋を入れてくれるサービスもありますので、
長年愛用したいという方はぜひ購入を検討してみてはいかがでしょうか。
お墓でのお水のお供えは水鉢に
お墓でお水をお供えする場合には、
柄杓などを使って水鉢にお水をたっぷりとお供えをします。
水鉢とはお墓前方にある楕円のくぼみのことで、お水をお供えする場所です。
基本的には花立ての間に設置されていることが多いですが、
供物台の一部に楕円のくぼみを作り、供物台と一体になっているものもあります。
お墓に水鉢がない場合、浄土真宗や神道などのお墓や、
デザイン性が重視されたお墓の場合には、
水鉢が設置されていないこともあります。
そういった場合は、湯呑などにお水を入れて供物台に置くようにしましょう。
但し、浄土真宗の場合はご先祖様や故人が
お水に困っていることはないとされているため、お水のお供えはいりません。
お墓参りでやってはいけないこと
他の仏事などと比べるとあまり作法が決められていないお墓参りですが、
やってはいけないこともいくつかあります。
墓石にお水をかけるのは構いませんが、
お酒やジュース、お茶などをかけてはいけません。
墓石がべたついてしまったり、シミが残ってしまったりする恐れがあります。
故人が好んで飲んでいたから、という理由で
ついやってしまう人もいるようですが、そういう場合にはお供えしてあげてください。
お水について 前編≫
カテゴリー

水をかける道具の種類
お墓に水をかける基本的な道具は水桶と柄杓です。
水桶(手桶ともいいます)とはその名の通り水を入れる桶で、
お墓参りでの水かけや暑い季節の打ち水などに使われます。
柄杓とは水をくむための道具です。
神社やお寺の手水舎で身を浄める際の道具として
置いてあるものをイメージしていただけると分かりやすいと思います。
これらは大体の墓地や霊園で誰でも使えるように貸し出されていますが、
そうでない場合には自分で用意する必要があります。
用意できない場合は、ペットボトルや綺麗なバケツも
水をかける道具として代用できます。
お墓参りで使う水桶と柄杓の値段
自分たち専用の水桶と柄杓が欲しい場合や、墓地や霊園での貸し出しが無く、
購入をしようと思っている場合には仏具店や
ネット通販、ホームセンターなどで購入できます。
プラスチック製や木製など様々な種類があるので、
値段も2000円前後から数万円前後まで幅広くあります。
水桶と柄杓のセットで売られていることが多いですが、
単体で販売されているものもあり、柄杓だけの値段だと300円前後から、
水桶だけの値段だと2000円前後から購入ができます。
できるだけ高いものを購入しなくてはならないなどのルールはないので、
自分が水桶に使うことのできる費用と相談して購入してください。
なかには水桶に家名や家紋を入れてくれるサービスもありますので、
長年愛用したいという方はぜひ購入を検討してみてはいかがでしょうか。
お墓でのお水のお供えは水鉢に
お墓でお水をお供えする場合には、
柄杓などを使って水鉢にお水をたっぷりとお供えをします。
水鉢とはお墓前方にある楕円のくぼみのことで、お水をお供えする場所です。
基本的には花立ての間に設置されていることが多いですが、
供物台の一部に楕円のくぼみを作り、供物台と一体になっているものもあります。
お墓に水鉢がない場合、浄土真宗や神道などのお墓や、
デザイン性が重視されたお墓の場合には、
水鉢が設置されていないこともあります。
そういった場合は、湯呑などにお水を入れて供物台に置くようにしましょう。
但し、浄土真宗の場合はご先祖様や故人が
お水に困っていることはないとされているため、お水のお供えはいりません。
お墓参りでやってはいけないこと
他の仏事などと比べるとあまり作法が決められていないお墓参りですが、
やってはいけないこともいくつかあります。
墓石にお水をかけるのは構いませんが、
お酒やジュース、お茶などをかけてはいけません。
墓石がべたついてしまったり、シミが残ってしまったりする恐れがあります。
故人が好んで飲んでいたから、という理由で
ついやってしまう人もいるようですが、そういう場合にはお供えしてあげてください。